

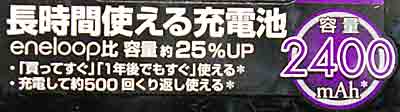
2年前発売の新型eneloopに比べ、容量25%アップで、その代わりに、繰り返し使用回数は500回に減りました。
他にも、自己放電の割合が通常eneloopに比べ多いとのことで、残存容量が1年後85%から75%に減っています。
2011年7月24日、暫定公開
2011年7月26日、容量の測定結果追加
2011年8月2日、1週間放置後の結果追加。
2011年9月1日、4週間放置後の結果追加。
2011年12月3日、3ヶ月放置後の結果追加。
2012年12月1日、1年放置後の結果追加
プロ向けのeneloopが発売です。


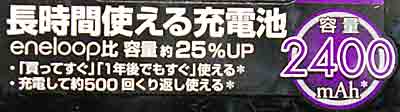
2年前発売の新型eneloopに比べ、容量25%アップで、その代わりに、繰り返し使用回数は500回に減りました。
他にも、自己放電の割合が通常eneloopに比べ多いとのことで、残存容量が1年後85%から75%に減っています。
これについても、サンヨーのサイトを見ると、1年後の容量は、もともとの容量が多い分、増えている、いうことを主張しています。
さて、実際に測定したところではどうでしょうか。私の予想では、自己放電量は1年後でも使えるが、実際のところは、電圧もそれなりに下がって、放置した時の性能は、普通のeneloopより落ちているというものですが、実際のところはどうなのでしょう。(この結果が出るのは1年後ですが。)
まあ、通常のニッケル水素電池と比べると、放置した場合の性能は、優れているのはさっきのサンヨーのサイトを見てもかいてありますし、evoltaの放置性能よりは、優れているとは思います。
まあ、プロ、と名前のつく以上、リモコンに入れて使うようなの用途には、適していないのは当然ですけどね。
充電、放電方法
自作の、パソコン制御ニッケル水素電池充放電器で、充電放電をしています。
1.放電条件: おおよそ500mAの、おおよそ定電流放電
1Vを下回ると、放電を停止しています。
2.充電条件: おおよそ2400mAの、まあまあ正確な定電流放電、1秒充電3秒休止の繰り返し
−ΔV検出よりちょっと前に充電は寸止め。(寸止め充電と充電効率の評価参照)
(記事中に強制充電と書いた場合は、満充電のチェックはしていません。)
おおよそ、っていうのが、どれぐらいおおよそなのかは、話が複雑なので、
1.定電流充放電特性と充放電電流測定値
をご覧ください。
充電、放電の間は、すべて、30分間の休憩をはさんでいます。
グラフの見方
slot1電圧 slot2電圧 slot3電圧 slot4電圧
slot1温度 slot2温度 slot3温度 slot4温度
slot1電流 slot2電流 slot3電流 slot4電流
つまり、同系統の色は同じスロット。明るいのが電圧、暗いのが温度と充放電電流です。 あと、測定はすべて1秒置きにプロットしており、例えば、1秒/4秒というのは、 1秒充電して、3秒休止、という意味です。なので、充電中の電圧を1回と休止中の電圧3回がグラフに表示されており、充電グラフの休止中のほうは、線が太く見えます。(拡大すれば、3本の線が見えます。)
今回のeneloopは、製造年月が2011年6月です。つまり、現時点で、1ヶ月経過しているということで、これまでのテストはほぼ3ヶ月だったのに比べると、非常に新鮮な?電池です。
早速、通常のeneloopと比べてみましょう。(比較対象に選んだのは、eneloopの旧バージョンです。最新のeneloopとeneloopの旧バージョンの比較はこちらで行っています。以下、特に説明のない限りは同じです。)
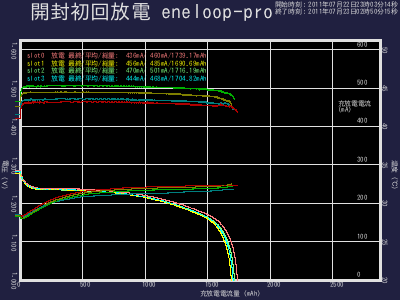 |
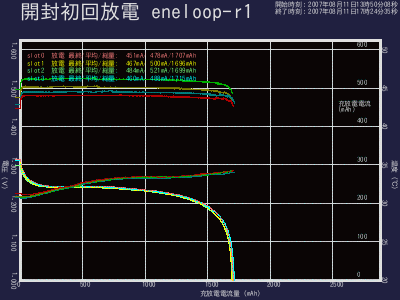 |
| 停止画像拡大:開封初回放電、2回目放電 3回目放電 | 停止画像拡大:開封初回放電、2回目放電 3回目放電 |
特徴的なことが何点かありますね。
1.3回目ともなると容量が多い。(これについては、次節の放電特性で議論。)
2.初回放電の容量が、かなり少ない。1.2V維持容量も少ない。
これは、製造後の自己放電が多いからか(でも1ヶ月)、最初から、満充電されていないかの、どちらかでしょう。
ただ、後述する、自己放電特性を見れば、その答えは出るかと。
3.バラツキが大きい。(これについても、後述する議論になります。)
いずれにせよ、ここで言えるのは、製造後1ヶ月のeneloop-proより、製造後3ヶ月の通常のeneloopのほうが、買ってすぐ使える容量は多いということになります。 (1.2V維持容量が重要な機器ではは特に差が出ます。)
通常のeneloopと比べてみましょう。
どうでしょうか。
1. 維持容量は、通常のeneloopより、スペック通り500mAhぐらい多い。
これについては詳細は後で議論します。
2. 1.2V維持容量は、通常のeneloopより400mAhぐらい多い。
逆に言うと、400mAhしか多くありません。つまり、eneloopの、放電末期の電圧がストンと落ちる傾向が
若干減っている、ということにもなります。
3. バラツキが大きい。(これについては、後で議論します。)
充電器から取り外してすぐに使用する分には、eneloop-proのほうが、長持ちする、ということは言えると思います。
充電特性については、微妙な結果に終わっています。
充電末期の電圧が急上昇するのがeneloopの特徴だったのですが、その特徴が若干薄れたようにも見えます。
ただ、容量が多いためにそう見える、というようにも見えます。
ただ、いずれにせよ、他の電池に比べると、やはり、末期に急上昇していると言えます。これとか。
一応、お約束ということで、いつもどおり、
2000mAh充電、(通常)寸止め充電、寸止め充電後200mAh追加充電、寸止め充電後460mAh追加充電
した後、放電して、容量を測定しました。
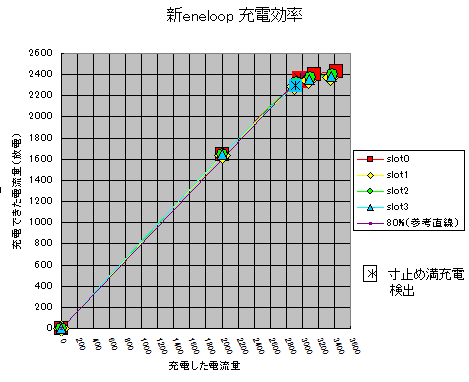
充電効率はいつもどおり80%程度。460mAh追加充電した時の容量は、平均2394mAhを確認しました。
なお、これもいつもどおりですが、この容量は少なめに出ていると思います。このあたりの事情の詳しくはこちらを参照。
私が所有しているeneloopの中で、バラツキは最大です。
なお、今回測定した容量(寸止め充電での容量)を、回路間偏差を取り除いて、いろんな電池で、比較してみましょう。
容量が25%増えたので、バラツキも25%増えると思いきや、それ以上にバラツキが大きくなっています。
ただ、今回は、この理由は寸止め充電の検出タイミングの違いが影響している可能性があります。
(充電グラフを見て、若干スロット1(赤)の電池が温度上昇が大きいところまで充電しています。つまり充電グラフでの赤色で示された電池の温度が充電末期に他のスロットより若干高くなっており、電圧上昇増加率が減ったタイミングが、実際他の電池より遅くなっている可能性です。
まあ、そのタイミングの違いも含めて、電池のバラツキだということも、言えるのですが、、、)
ということで追加充電した状態も含め、比較も載せました。
| 電池0容量 (mAh) |
電池1容量 (mAh) |
電池2容量 (mAh) |
電池3容量 (mAh) |
最大と最小の容量差 (mAh) |
容量差/ 平均容量比 |
||
| eneloop-R | テスト1 | 1828 | 1825 | 1824 | 1830 | 5.4 | 0.30% |
| テスト2 | 1825 | 1824 | 1821 | 1826 | 4.4 | 0.24% | |
| テスト3 | 1823 | 1822 | 1819 | 1823 | 4.0 | 0.22% | |
| eneloop-R 3回の平均 | 1825 | 1824 | 1822 | 1826 | 4.6 | 0.25% | |
| evolta | 1913 | 1893 | 1896 | 1879 | 33.7 | 1.78% | |
| eneloop-Rgrey | 1826 | 1849 | 1858 | 1847 | 31.5 | 1.71% | |
| 新eneloop | 1850 | 1833 | 1818 | 1817 | 32.7 | 1.79% | |
| eneloop pro(寸止め) | 2350.7 | 2297.2 | 2320.5 | 2299.3 | 53.5 | 2.31% | |
| eneloop pro(200mAh追加充電) | 2395.2 | 2349.3 | 2372.0 | 2352.4 | 45.9 | 1.94% | |
| eneloop pro(460mAh追加充電) | 2421.1 | 2378.0 | 2400.0 | 2377.5 | 43.6 | 1.82% | |
(*) 容量差/平均容量比 = 最大と最小の容量差 / 電池0から3の容量の平均
追加充電した場合のバラツキ(1.82%)は、新eneloop(1.79%)と同等ですね。通常の寸止め充電のバラツキ(2.31%)は大きいですが。
ということで、結論としては、やはり、充電末期の電圧上昇の状況にも、バラツキがある、ということになります。
なお、いつも書いていることですが、たかだか4本のバラツキを測定したからといって、これで、統計的に正しいとはいえません。
ただ、これまでのさまざまな実験結果から、最近のeneloopは、バラツキが大きくなってきた、というのは言ってもいいような気がしています。
比較対象として、4年前購入のeneloop-R購入直後に放置実験した結果と比較しています。
季節的にも、ほぼ同時期です。(グラフの開始時刻、終了時刻のところを見てください。また、放電中に測定される温度も、参考程度にはなるでしょう。)
| eneloop-pro | eneloop-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
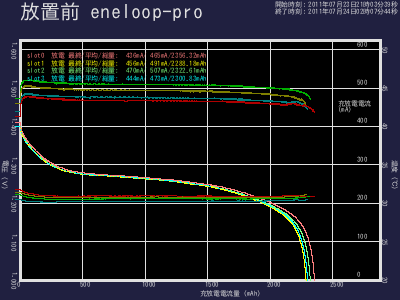 実験中です。 実験中です。 |
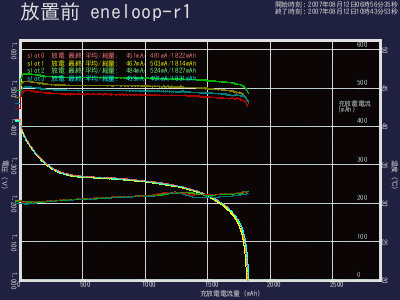 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大画像:放置前 1週間放置後 4週間放置後 3ヶ月放置後 1年放置後 | 拡大画像:放置前 1週間放置後 4週間放置後 3ヶ月放置後 1年放置後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残電流量比較:
|
残電流量比較:
|
1週間放置後の残存容量は、平均92.4%(eneloop-Rは93.5%)と、eneloop-Rと大差ありませんね。
一方4週間後には、88.5%(eneloop-Rは91.6%)と、少し、開いてきています。
3ヶ月後には、85.5%(eneloop-Rは91.1%と、さらに開きがでました。
1年後には、79.37%と、86.3%というように、さらに、差が開いています。
容量で言えば、最初490mAhの差だったのが、一週間後には440mAhの差、4週間後には、390mAhの差、3ヶ月後には、310mAhと、差は縮まっています。
ただ、1年経過しても、差は、259mAhと、eneloop-proは優位を示しています。
1.2V維持容量は、差が縮まって、来ており、丁度3ヶ月で、ほぼ同じになって、1年後には、逆転されています。
1000mAhあたりまでの維持電圧は、すでに3ヶ月後には、明らかに、eneloop-proは、eneloop-Rより低くなり、1年後には、その広がっています。
やっぱりプロ向けの電池と言えるのかがポイントです。
電池の特性を把握した、いわゆるプロの使い方しないと、優位性はひきだせないのではないか、という可能性です。
そしてその場合に、通常のeneloopに比べ、優位性(=容量だけ)が、どの程度あるのかがポイントかと。
で、結果として、充電して、4週間ぐらいまでは、明らかに、優位です。3ヶ月目になると、用途によっては、eneloopのほうが優位な場合も若干あるけど、ほとんどの場合は、eneloop-proのようが優位、という結果です。1年後には、維持電圧の点で、eneloop-proのほうが、不利といっていいと思います。
結論として、高い値段払って、性能を生かす、という意味では、やはり、プロ向けの電池かと思いますが、そこそこ素人的な使い方をしても、問題がないように、仕上がっている製品だと思います。
なお、1年放置後の、パナソニックサイトの、eneloop-proの残容量は85%ですが、今回、1年後では、79.37%という数値になっています。eneloop関連で、このような実験結果(つまり、私の測定値より、いい値が表示されている。)というのは、実際始めてです。ちなみに、この電池が発売されたときは、1年放置後の容量は75%ということになっていましたが、なんでなんでしょうね。
1年の間に性能が上がり、最近買う新しいロットだと、それだけの性能が出るのか、
パナソニックになって、数値の表示が変わったのか、
本音を言うのであれば、sanyoにいたころのeneloopは、一般家庭の条件ぐらいにあわせて、控えめに、性能を表示していたと思います。
panasonicに買収されてからは、ちょっと、一般使用とは、かけはなれた数値を表示するようになりましたね。(一般家庭で、20℃で1年放置なんてありえないので、まあ、嘘ではないんですが、sanyoにいたときの、eneloopの表示は、私の実験結果(室温放置)より、かすかに控えめな数値でした。)
ま、以上は、少し邪推がはいっていることは、否めません。sanyoから、panasonicに買収された事実と、eneloop-proとeneloopの性能差、ロットの違いによる差が混じった結果になっていますので。
ただ、来年の3月23日に、新型eneloop HR-3UTGBの評価において、1年放置後放電実験をするので、そこで、の新型eneloopの性能が明らかになり、eneloop-proとeneloopの性能差による違いは排除されると予想します。つまり、sanyoから、panasonicに買収されたことによる、公表数値の会社の方針の違いなのか、ロット差による、性能の違いなのかに絞られると。
え?、、、ロット差による性能の違いを否定するためには、また、新しいeneloopを買って実験しなきゃいけない、、、ってこと(笑)